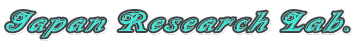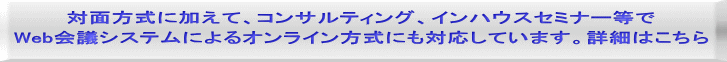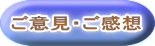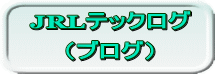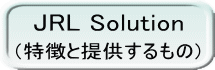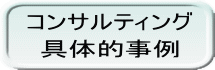新規事業・商品企画から研究開発推進、現場の課題解決・改善、そして、人材育成まで
ジャパン・リラーチ・ラボ(JRL)は、明日の飛躍をお手伝いいたします。

トラブル・不良分析・異物分析
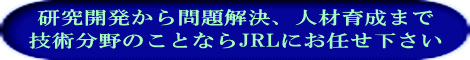
異物分析と一口に言っても様々なものが、その範囲はきわめて広いものとなります。ここでは、その中の一例として、最も典型的なものの一つである何らかの固体が対象物内に存在するような場合を考えてみたいと思います。
まず、問題になるのは異物のサイズです。肉眼で容易に確認できるほどのサイズなのか、光学顕微鏡が必要なのか、または、パーティクルアナライザーや走査型電子顕微鏡(SEM)のような物が必要なのかということで切り分けることになります。それによって初期アプローチが異なってきます。ただし、いずれの場合も共通することは、まずは観察、すなわち、見ることがファーストステップになるということです。
サイズの確認はもちろんのこと、形状(球形、異形、多角形など)、厚み、光学観察できる場合には色も含めた形態を詳細に確認することがまず最初に行うべきことになります。当たり前のことのように思うのですが、現実にはこの部分が不十分なことが多く、その重要性が気付かれていないことが多くあります。
ほとんどのところで、光学顕微鏡程度は保有していることが多いと思います。また、SEMについても、最近では非常にコンパクトで操作も簡便で、コーティング処理なしで有機物も観察可能な安価な物が開発されていますから保有しているところも増えてきています。そういう意味では、この重要なファーストステップをすぐに実行できる環境が整ってきているといえます。
異物分析における最終目的は、異物が発生しないようにすることですが、そのための情報として異物の特定とそれによる発生源の特定があげられます。この段階で多くの方は、異物の組成の方に注意が集中することが多いのですが、確かに最終的には組成が必要になってくる可能性は高いと思います。しかし、実は形態観察だけでかなり原因を特定できることが少なからずあります。
泡の場合を除いて、真球に近いような形状の場合、自然由来物である可能性は低く人工物である可能性が高いだけでなく、その特徴的な形状から由来を想像できる可能性が非常に高くなります。また、油滴状、繊維状なども特徴的であり、その形状だけで原因をかなり絞り込むことが可能になります。そして、ある程度対象物を絞り込むことができれば、この後の分析方針を決めていく過程においておおいに参考になります。
このように、ファーストステップとして詳細に形態観察を行うことは、比較的簡便に実施できることにもかかわらず、想像以上に情報を得ることができ、場合によってはその後の分析方針を左右するほど重要なものであるといえます。
|
異物の正体が知りたい |
XPSでは、有機物などの絶縁物も測定できる事を特徴としているが、厳密にはX線照射によって試料から電子が放出されることから、絶縁物の場合には徐々に正に帯電するチャージアップ現象が起きてしまう。チャージアップが起きるとスペクトル全体のシフトやピークの歪みなどが誘発される。そのため、一般にはフラッドガンと呼ばれる低加速の電子線シャワーを照射する中和銃が装備されており、これによってチャージアップを補正することになる。
さて、ここで形態観察も含めて異物分析においてポイントになることの一つとして、対象物が限られているということがあげられます。場合によっては、その一点しか存在しないということも珍しいことではありません。したがって、特に初期ステップにおいては、原則として非破壊分析であることが優先されます。基本的には、非破壊分析で追い込めるところまで追い込んで、最後の確認では破壊分析も選択肢に入れて追い詰めるということになります。
分析手順を左右するものには、形態(サイズ)の他にも、「有機物、無機物」、「固体、液体、気体」などがあげられますが、異物が露出しているかどうかも重要な要素となります。すなわち、異物が露出していれば表面分析などの分析手法を用いることができますが、埋もれている場合にはそのままでは適用困難となります。このような場合には、内部も分析できるバルク分析手法を用いたり、マイクロサンプリングなどの技術を用いて異物を露出、または、取り出す必要があります。もちろん、この場合にも異物を破壊して良いかどうかは重要な要素となります。
しかし、十分な事前情報を得られないケースも少なからずあります。例えば、有機物か無機物かの予想が形状などからだけでは困難なケースです。このような場合には、無機物を対象とする手法、有機物を対象とする手法の両方を行うということも考えられますが、コストの問題や異物が一つの場合には時間がかかってしまうという問題もあります。したがって、通常は有機物も無機物も対象とできるような手法、例えば、X線光電子分光法(XPS)などを選択しておよその当たりをつけて、その上で詳細分析に進んでいくという方法が有効になります。
また、異物と表現しますが、必ずしも外来のものとは限りません。正常部が変質したものであるということも珍しくありません。組成的には周囲と変わりないが、僅かな屈折率の違いで異物として認識されているだけということもあります。そのような場合に、組成の違いをいくら見つけようとしても無駄な時間とコストを浪費するだけになってしまいます。したがって、一つの方向に囚われるのではなく、絶えずあらゆる方向からの可能性を考えながら分析を進めていく必要があるのが異物分析なのです。
異物分析では、形態なども非常に重要な情報であることは先に説明したとおりですが、やはり組成に関する情報というのが最も重要なものの一つになります。組成を得る事ができる分析法には様々なものがありますが、異物分析においてはある程度小さな領域に絞った分析ができるということが条件の一つになります。代表的なものとしては、以下のようなものがあげられます。
|
それぞれに一長一短があるので、これらを的確に選択していく必要があります。そのためにも、本格的な構造解析に入る前にできる限りの情報を得る努力をすることが重要になります。軽い思い込みで、機械的に例えば顕微赤外分光法の担当者に相談したがばかりに、十分な情報が得られない結果に終わってしまうというようなことは絶対に避けなければなりません。
また、選択可能な分析手法の幅を広げる意味や、より詳細な情報を得るために、異物をサンプリングすることが有効なことも多くあります。特に、露出しておらず異物が埋没しているような場合には重要なプロセスとなります。従来は、マイクロサンプリングは顕微鏡下で熟練した技術者が手でサンプリングを行っていましたが、最近では高性能なマニピュレーターも多数開発されているので、マイクロサンプリングも幅広く行われるようになってきました。ただし、この場合も作業としては簡便になってきているのですが、試料に手を加えるということには違いは無いので、全体像をきちんと把握してアーティファクトを生まないように実施する必要があります。その意味で、安易に実施できるようになってきた状況というのは簡単に喜んで受け入れられるものではないとも言えます。
異物分析においては、対象物の数や量が少なく、やり直しができないことが多々あります。にもかかわらず、初期ステップではベールに包まれた状態で触れることなく、異物の素性を想像しなければならないという難しさがあります。だからこそ、材料やプロセスはもちろんのこと、分析のことも十分に把握したエキスパートに相談することが重要なのです。
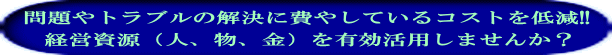
ご相談、お問い合わせは、まずは下記までお気軽にお問い合わせ下さい

総合技術コンサルティング&人材育成
ジャパン・リサーチ・ラボ