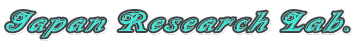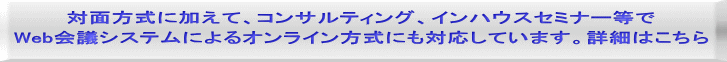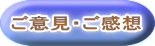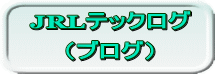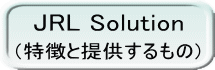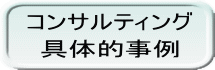新規事業・商品企画から研究開発推進、現場の課題解決・改善、そして、、人材育成まで
ジャパン・リラーチ・ラボ(JRL)は、明日の飛躍をお手伝いいたします。

問題解決・課題解決におけるポイント
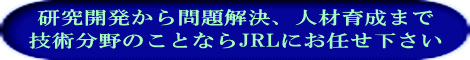
ビジネスの世界では、日常的に様々な問題や課題が発生し、それらを速やかに解決しなければなりません。しかし、問題や課題があることは実は決してマイナスばかりではありません。それらが解決されるからこそ進歩発展が生まれるのです。言い換えるなら、課題や問題は進歩発展のための糧であるとも言えます。問題・課題解決におけるポイントには数多くのことがあります。今回はその中でもコアとなるもの、重要となるポイントについて、いくつか紹介します。
課題や解決するにおいてまず重要となるのは、問題や課題に関わる要因、要素等(例えば、原因)について、「コントローラブル(コントロールできるもの)」と「アンコトローラブル(コントロールできないもの)」の区別を行うことです。すなわち、自分たちでどうにかできることと、どうにもできないことを切り分けるという作業が必要です。例えば、どれぐらいの時間どのタスクに割り当てるか、すなわち、いわゆるエフォート率は自分たちの裁量範囲であると言えます。一方で、法規制等や社会情勢の変化はもちろん、競合の動向は自分達ではどうにもできないと言えます。
前者のコントローラブルなものについては、如何にして望む状態、最適状態にするかということを十分な時間をかけて検討することが要求されます。しかし、後者のアンコントローラブルなものについては、いくら時間をかけて考えたところで思うように扱うことはできず、また、簡単に状況が変わってしまいます。従って、このようなものについてはその存在を把握することと、可能な限りのリスクヘッジの準備をするということが必要となります。
|
現場が経験と勘に頼っている |
また、業務における多くの問題・課題は極めて複雑になっていることから、チームや組織などの集団で対応することが必要となります。このような時に重要となるのが、最初の段階で、メンバー全員で問題・課題の定義、目的(なぜその課題や問題を解決するのか)、ゴール(どういう状態を目指すのか、その課題や問題を解決することによって得られるもの)を共有することです。それぞれが、異なる目的やゴールを意識していては、当然のことながら集団の力、シナジーが発揮されません。
そして、実際の問題・課題の解決においては、まず、現状と理想状態の差異(ギャップ)を可視化することが必要となります。これによって、解決すべき問題・課題が明らかになって、明確に定義されます。それらが定義されて初めて原因、障害(邪魔するもの)といった対象が定まり、具体的な解決プロセス、対応(対策)を考えていくことができます。これは、対象範囲、すなわち、スコープを決めることです。このようにスコープを定義しておかないと、どんどん発散していってしまい、最終的には手に負えなくなります。
また、問題や課題そのものはもちろん、その要素も複数存在することも少なくありません。したがって、最もクリティカルなもの、最も重要なものはなにかということを検討することも必要となります。限られた時間、リソースの中で必ずしも全てを同時に対処することはできません。だからこそ、優先順位が重要となるのです。
これらは問題、課題の解決だけでなく、戦略策定や仮説構築など種々の場面で重要なキーとなる考え方です。
世の中には熟練工と呼ばれる人たちがいます。彼らは、常人には計り知れない経験と勘で様々な問題を解決します。例えば、製造プロセスでトラブルが起きた時、彼らはそのトラブルによって発生した不良品をしばし眺めた後、おもむろに製造プロセスの条件をゴソゴソと調整してトラブルを解決してしまいます。
経験者の勘は豊富な経験に裏打ちされたものであり、博打とは一線を画すものです。そういった点においては、日本の製造業はそういった熟練の技、テクニックに支えられて成長してきたという側面は否定できません。しかし、このことは必ずし諸手を上げて喜んでよいものというわけではありません。
テクニックとは個人の属するものであり、その正体は文字通りブラックボックスの中に包まれています。そして、技術者の観点で見たときに最も恐ろしいのは、そのテクニックを駆使する本人達でさえその内実を理解できていないということなのです。そうです、本人達もなぜそのトラブルが起きたのか、そして、なぜ解決できたのか分からないのです。ただ、自分の勘に頼って調整したら上手くいったとしか説明できないのです。
これは、技術の継承という意味での問題はもちろんのこと、同類のトラブルが再び起きた時に必ずしも解決できるとはいえません。結果として現れてくるトラブル自体は同じであっても、その原因も同じであるとは限らないからです。また、別の場所で同じような問題が起きた時も本人がいなければ解決できないのです。
|
|
世の中の全ての事象には原因、理由が存在します。しかし、経験と勘に頼ったテクニックには、原因の追求という概念は存在しません。そこにあるのは、理由はどうあれ、理屈ではなく何をやっても、それが本人でさえ何をやっているか分かっていなくても解決できた良いということだけなのです。
原因を突き止め、その原因に沿った論理的な対策を行ってこそ、類似の問題にも誰でもが対処できるようになるのです。そうなって初めて、テクニックではなく技術となり、知識となるのです。そうやって、やっと問題が解決できたということになるのです。
研究開発においても同じとこです。実験の結果が上手くいっても、いかなくても、そこには必ず理由があります。良くは分からないが上手くいったからと先に進んでしまっては、問題が発生したときに何も対処できず、また最初に立ち戻って考え直すという堂々巡りをしなければならなくなります。なぜ、上手くいったのか、ポイントはなんだったのか、上手くいかなかった理由はなんなのかをその都度解決していってこそ、実験が完了したことになるのです。
テクニックや運に頼るのではなく、論理的裏づけの元に進んでいくことが、足元の土台を固め着実に前進していくための方法なのです。そして、その論理的道のりは、客観的事実と結果によってのみ進んでいくことができます。これらを得るための手段が実験であり、その手段が分析なのです。
分析によって客観的事実であるデータを得て、それをもとに論理的判断を下すというプロセスを繰り返すことで、最終ゴールへの最短で最善の道程を進んでいくことができるのです。すなわち、言い換えるならば、分析を有効に活用できて初めて真の最終ゴールに到達する事ができるのです。
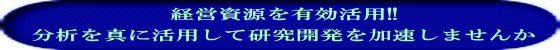
ご相談、お問い合わせは、まずは下記までお気軽にお問い合わせ下さい

総合技術コンサルティング&人材育成
ジャパン・リサーチ・ラボ