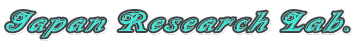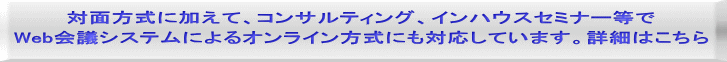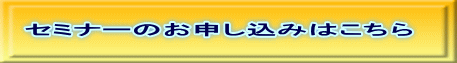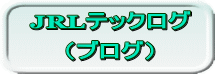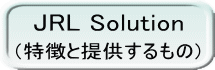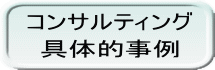新規事業・商品企画から研究開発推進、現場の課題解決・改善、そして、人材育成まで
ジャパン・リラーチ・ラボ(JRL)は、明日の飛躍をお手伝いいたします。

暗黙知の形式知化と行動心理による進化型技術継承の方法セミナー・講習会
~組織と技術の自律的成長を生む技術継承の戦略と方法~
| 技術を繋ぎ、発展させる技術継承 人を育てる技術継承 技術継承による継続的発展と成長 |
技術継承における2007年問題は誰もが知るところですが、あれから多くの時間が過ぎた今でも技術継承に苦しんでいる企業が数多くあります。この背景には、雇用延長や再雇用といったパッチワーク的でその場しのぎの対策による問題の先送りなどの方法論的な問題はもちろん、技術継承というもの自体に対する間違った認識があります。
本来の技術継承とその目的は何か、何をどのように伝えなければならないか、そして、なぜ技術継承は難しいのか、上手く行かない理由は何かという技術継承の本質を考えなければ未来永劫同じ問題を繰り返すことになります。技術継承は単なる技術の引継ぎではありません。
本講演では、技術継承の本質の理解と共に、発展的成長へと繋がる技術継承の考え方、そして、その戦略を実現するための具体的方法(伝える内容、伝え方、技術の情報化)について、暗黙知と形式知という考え方や行動心理学の考え方を取り入れて解説します。
受講者の声
|
JRL主催セミナーはセミナー会社等との共催では含まれない、実施されない
・追加の内容、解説
・例題や演習等の追加
・講義中に実施した演習の回答に対するコメント、アドバイス
・お申込みがお1人でも原則として開催(中止による面倒な事務処理が不要)
が含まれ、より詳細に深く学び、実務での活用を促進することができます。
また、主催セミナーだけの特別受講特典も利用することが可能です。
| 実施日 | 2026年9月8日 10:30-16:30 |
| 実施方式 | Web配信(Zoom) |
| 受講料 | 税抜き49800円(税込み54780円)、テキスト付 |
| 講師 | ジャパン・リサーチ・ラボ 代表 博士(工学) 奥村 治樹 |
| 備考 | 【ZoomによるLive配信】 ・本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。 ・お申し込みにあたり、接続確認用URL(https://zoom.us/test)にアクセスして接続できるか等ご確認下さい。 ・後日、別途受講用のURLをメールにてご連絡申し上げます。 ・セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご受講ください。 ・リアルタイムで講師へのご質問も可能です。 ・タブレットやスマートフォンでも視聴できます。 |

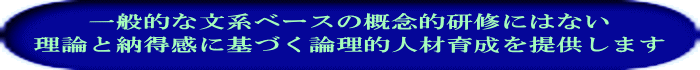
|
|
特徴
|
主な内容
| 【技術継承と暗黙知】 開発技術に限らず技術継承のコアでもある暗黙知について、本当の技術継承とは何かというところから解説します。 ・技術継承とは ・暗黙知の定義 ・暗黙知の構成要素 ・暗黙知の利用 ・情報資産 など 【継承の目的】 やらされ仕事、単なる作業で終わらせないために、技術継承に関わる人達が理解しておくべき技術継承の目的について改めて整理します。 ・なぜ継承するのか ・サスティナビリティー ・ダークスポット ・暗黙知の活用と応用・発展 ・継承と効率化・発展 など 【なぜ継承が難しいか】 技術継承が上手くいかないという問題解決を行う上でその認識が必要不可欠な、なぜ技術継承が上手くいかないのかという原因について解説します。 ・情報化の難しさ ・内面の可視化 ・大いなる誤解の存在 ・継承における心理的課題 ・現場担当者任せの組織の課題 ・ダメなパターン など 【技術継承における課題】 技術継承を進める上で障害となる組織、現場の課題について解説します。 ・本質的課題 ・現実的な現場の課題 ・伝える側の課題 ・受け手 ・責任と原因の帰属 ・アウトソーシングの罠 ・雇用延長、再雇用の弊害 など 【継承プロセス】 実際の技術継承プロセスを示すと共に、継承技術を可視化するために必要不可欠な質問テクニックや可視化の方法などについて解説します。 ・技術の顕在化 ・顕在化のポイント ・重要な顕在化の方法 ・ヒアリングとインタビュー ・4Q ・質問のポイント ・フロー化 ・トップダウン&ボトムアップ ・フローの深掘り など 【継承のキーポイント】 技術継承する上でどこに注目すべきか、抜け落ちがちな部分、そして、伝えるテクニック、関わる伝え手と受け手の考え方などの技術継承の実務における重要ポイントについて解説します。 ・形式知化の向こう側 ・技術の本質 ・経験知 ・技術力の継承とは ・スキル以外に継承する本質 ・継承の内的プロセス ・スタートとゴール ・伝えること ・人を動かす伝え方 ・熟練者とは何か ・2種類の熟練者 ・新米、中堅、ベテラン ・ジェネレーションギャップ ・業務化 ・バランス ・特異点の重要性 ・二つの成長 など 【継承を成功させる戦略】 1回で終わりではなく、時間や労力を必要とする技術継承をスムーズに行っていくために必要となる技術継承戦略の考え方について解説します。 ・継承の要件 ・戦略との整合 ・優先順位 ・対象の取捨選択 ・ステップ継承 ・増える技術への対応 ・分散・冗長化 ・継承のPJ化 など 【継承の準備】 技術継承をスムーズに進めるために必要となる技術継承の準備について解説します。 ・意識統一 ・棚卸 ・技選 ・選別 ・人選 など 【手順、スキル以外の伝えるべきこと】 うわべの手順だけを伝える中身の無い継承としないために、伝えるべきことについて解説します。 ・ソフト要素 ・職人の判断 ・感性の情報化 ・内面の情報化 ・感性の可視化 など 【技術(ナレッジ)の可視化・情報化】 外面だけからは分からない、しかし、継承すべき技術の内面、本質をいかにして引き出し、可視化するかについて解説します。 ・暗黙知の情報化とは ・外面(手順)の情報化 ・パラメーターの可視化 ・生体情報の可視化 ・情報化の基本プロセス ・数値化の方法 ・多元的収集と情報次元の拡張 など 【技術継承の方法(伝え方と教え方)】 伝え方、教え方を中心に具体的にどのように技術継承を行うのかに加えて、継承実務のコアとも言えるOJTについてなぜうまくいかないのか、正しいOJTとはどのようなものなのかについて解説します。 ・継承のパターン ・継承技術のブレークダウン ・認知バイアスの罠 ・まず知る ・OJTが機能しない理由 ・正しいOJT ・良い訓練とは ・ソクラテス式 ・以心伝心 ・「動」で伝える ・徒弟制度 など 【継承のためのコミュニケーション】 技術継承を単なる手順のやり取りで終わらせないために必要不可欠なコミュニケーションについて解説します。 ・コミュニケーションとは ・心(マインド)のリンク ・伝えたいこと、聞きたいこと など 【育成と継承】 人材育成でもある技術継承において求められる育成的観点について解説します。 ・時代・社会の変化 ・伝える側の教育 ・受け手の事前教育 ・メンタリティー ・アフターフォロー ・オーバーラップ など 【補足ポイント】 よりスムーズに、効率的に、確実に開発技術を継承するために必要なポイントを補足解説します。 ・記録と継承 ・開発、モノづくりへのフィードバック ・継承だけで終わらない ・非属人化の日常化 など 【まとめ(継承のゴール)】 ・継承の基本フロー ・継承プロセスの改善 質疑 |
セミナー内容の一部がHP記載と変更になる場合があります。
ご相談、お問い合わせは、まずは下記までお気軽にお問い合わせ下さい

総合技術コンサルティング&人材育成
ジャパン・リサーチ・ラボ